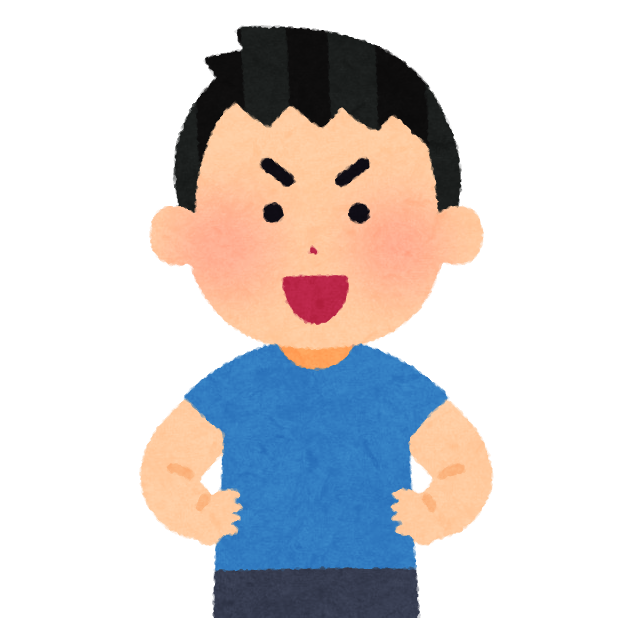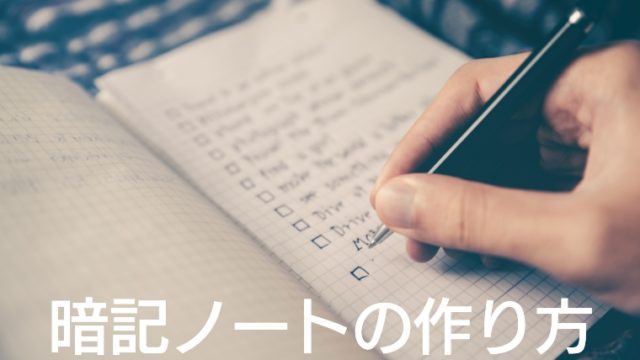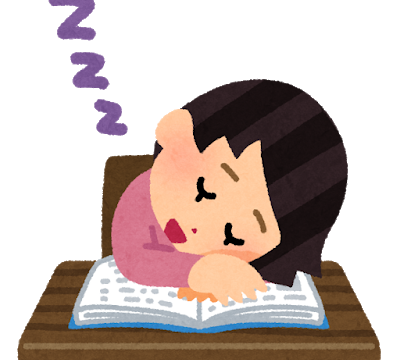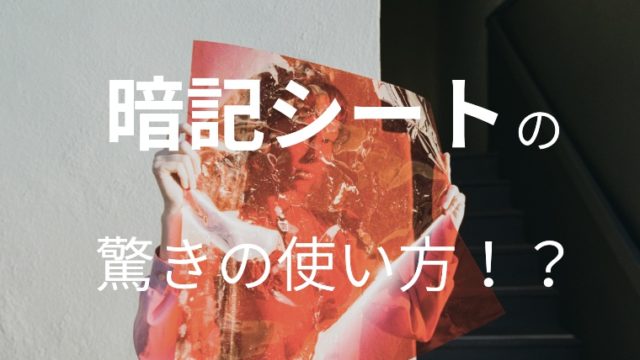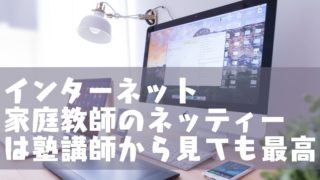勉強の効率を高めるためには目標設定が大切です。
でも実際に目標を決めようとすると結構難しいと思いませんか?
ネットや本を参考に目標を設定しても、自分に合わず結局意味のないものとなってしまうこともあります。
というわけで今回は、勉強の目標の立て方について紹介していきます。
目的別の目標の決め方の例も紹介していきますので、ぜひ参考になさってくださいね。
《挫折しない!》勉強の目標を決めるポイントとは?

それでは早速、勉強の目標の立て方を紹介していきます。
基本的には《大きな目標→小さな目標》と決めていく
目標を決める順番としては、
大きな目標 → 中間目標 → 小さい目標
の順番で決めていくのがポイントです。
だいたいの人は受験など期限のあるものに挑戦しますからね。
ここで言う「大きな目標」とは「最終的なゴール」という意味です。
人によって目指すべきところは違いますので、壮大な目標を決める必要はありませんよ。
例えば…
- キャビンアテンダントになりたい
- 志望校に合格したい
- 勉強の習慣をつけたい
これらのどれもが「大きな目標」となり得ます。
逆に「小さな目標」から考える場合もある
でも、まだ「大きな目標」を持っていない人も多いことでしょう。
例えば小学生の低学年だとまだ具体的な夢もないでしょうし、受験などタイムリミットとなるものも当面はありません。
こんな風に明確なゴールやタイムリミットが存在しないのなら「小さな目標」から考えていくのも手です。
「小さな目標」は1日の中で完結できるものにしよう
大きな目標から考えた場合にも、小さな目標から考える場合にも共通することですが…
この「小さな目標」は1日の中で完結できるものにするのが理想です。
例えば…
- 毎日○時間勉強する
- テキストを1日に○ページ進める
- 夕食の前に宿題を終わらせる
- 毎日必ず英語に触れる
などが考えられます。
こんな風に1日単位まで落とし込むことで具体性が増し、大きな目標に対してどれくらい近づいてるのかが分かります。
目標が決まったら具体的な勉強計画を立てよう
こんな感じで目標が決まったら…
目標を叶えるためにどんな勉強をしていけばいいのかを考えていきましょう。
特に受験生はしっかりと計画を立ててくださいね。
ここではかなり具体的に、
- どのテキストをどんなペースで進めるか
- 基本的タームはどう設定するか
- 確認テストはどのように行うか
なども決めていきます。
詳しくはこちらの記事で解説していますので、参考にしてみてくださいね。
自分で決めた目標であること
やはり目標は自分で決めたものではないといけませんね。
親や先生が決めた目標ではどうしてもやる気が出ないものです。
でももし自分の決めた目標だったら…
クリアできた時の達成感も味わうことができますし、その次の目標ができても前向きに頑張ることができます。
クリアできなかった時も誰かのせいにすることはないでしょう。
もし自分で目標を立てることができないような学年の子だったら親や先生が手伝っても良いでしょう。
しかしくれぐれも、本人の意思を尊重してあげないといけません。
大人の主観や要望が強すぎると、プレッシャーに感じてしまったり自主性が損なわれてしまう可能性があります。
頑張れば絶対に達成できる目標を設定する
例えば今の時点で30点しか取れていないのに、いきなり「次のテストで90点」なんて目標では無理がありますよね。
難しい目標はやる気をなくすことにもつながります。
大切なことは、頑張れば必ず達成できる目標を設定すること。
「小さな目標」や「中間目標」を一つずつクリアしていくことによって着実に「大きな目標」に近づいていくことが必要です。
できるだけ数字を使った目標設定をする
という目標の決め方をしてしまうと、本当に達成できたのか分かりませんよね。
なので目標を決める際はできるだけ数字の入った目標にすることがポイントです。
例えば…
- 次回のテストで80点を取る
- 1日最低1時間勉強する
- 単語を1日○個覚える
- 次回の模試でA判定を狙う
こんな風にいろいろな目標が考えられます。
きちんと数字が入った目標を設定していれば、誰から見てもその目標が達成できたか分かります。
そしてその目標を達成するための具体的な勉強方法も絞れていくはずです。
【目的別】勉強の目標の立て方を例を用いて解説!
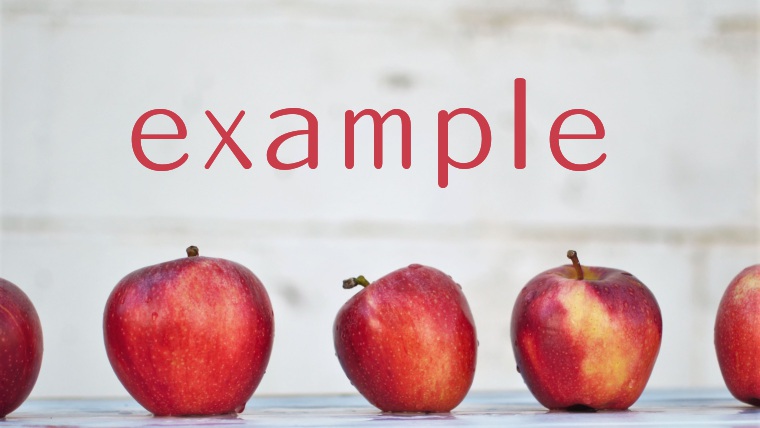
それではこれまでの解説をもとに、目標の立て方の例をいくつか紹介していきます。
中学3年生のAさんが英語の勉強目標を立てる場合
大きな目標:入試本番で英語を8割得点する
↓
中間目標:○月までに単語と文法を完璧にする
↓
小さな目標:単語は1日10個暗記、文法は毎日2ページ進める
こちらは基本の通りに、「大きな目標」→「小さな目標」の順番で考えました。
このようにいくつかの中間目標のようなものを設定しても構いません。
そして「小さな目標」は中間目標を叶えるための具体的な行動目標としました。
これはあくまで例なので、今の自分の実力や志望校によって勉強内容の調整は必要です。
小学2年生のBさんが日々の家庭学習の目標を立てる場合
小さな目標:夕食の前に宿題を終わらせる
↓
その次の小さな目標:宿題のほかにテキストを自分で進める
↓
大きな目標:自分から勉強する習慣をつける
小学校低学年のように、当面タイムリミットとなるものがない場合はこのように決めても良いですね。
一度決めた小さな目標をクリアしたらその次の小さな目標…といった感じ。
どんどん「小さな目標」を更新していくイメージです。
大前提として「自分から勉強する習慣をつける」という大きな目標があったとしても、そこに行きつくまでの正解はありませんからね。
高校1年生のCさんが大学受験を見据えた勉強目標を立てる場合
今度は受験までは時間があるけども、しっかり実力を伸ばしていきたい場合について見ていきましょう。
《大きな目標》MARCHレベルの大学に合格する
↓
《中間目標①》
- せっかく身に付けた勉強習慣を継続する
- 国・英・社は最終的に受験レベルまでもっていく
- 推薦も視野に入れて定期テストも上位を取りたい
↓
《中間目標②》
- 毎日予習・復習・受験勉強のどれかを行う
- 受験で使う科目は市販テキストも進める
- 定期テストは必ず8割以上とる
↓
《小さな目標》
- 普段は1日2時間、テスト前は1日5時間勉強する
- 市販テキストは1日最低1ページ進める
- 学校で習ったことはその日のうちに定着させる
上の例では「大きな目標」を達成するために必要なものが「中間目標①」、
「中間目標①」を達成するための目標が「中間目標②」、
そして「中間目標②」を達成するための行動目標が「小さな目標」となっています。
こんな風に「大きな目標」がレベルの高いものだったり今の自分から遠いものだと、それを叶えるためにするべきことも沢山できてしまいます。
将来キャビンアテンダントになりたいDさんの場合
ここまでは理想のやり方に従って目標を考えていきましたが、堅苦しく感じる人もいるでしょう。
そんな人はこんな風に目標を決めることもオススメです。
- キャビンアテンダントなりたい!
- そのために、大学は外国語学部に進みたい
- 英語で良い点数を取らなくてはいけない
- 1年後には定期テストで90点取る!
- そのためにまずは次のテストで70点!
こんな感じのざっくりとした目標設定でもOKです。
ここには行動目標が入っていないので別途考える必要がありますが…
単に目標を決めるだけならこれくらいのものでも良いでしょう。
とにかくまずは目標を作ることで意識を変えることができます。
ぜったいに目標達成するための工夫

次に目標を達成するためにできる様々なアイディアを紹介していきます。
せっかく決めた目標を絶対に達成するために工夫していきましょう!
目標と進捗状況を「見える化」しよう
せっかく決めた「大きな目標」や「小さな目標」、そしてその進捗状況はいつでもチェックできるようにしておくと良いですよ。
特に手帳やカレンダーに目標を書いておくことがオススメです。
そしてそれを見える位置に置いておけば家族と共有することもできます。
また目標や進捗を見える化することで、できていない部分や目標までの距離感も見えてくるはず。
計画の修正をする際の参考資料にもなります。
勉強のための環境を整えよう
せっかく目標を設定しても、勉強に不向きな環境ではどうしても集中することができません。
なので普段勉強する環境を整えていくことも大切になりますよ。
例えば…
- 机の上をきれいにする
- ゲームや漫画などを見えないところに隠す
- プリントを探しやすいようにファイリング
- テレビなどの雑音が聞こえないようにする
などが考えられますね。
こういった準備をしておけばいつでも勉強モードに入ることができます!
こちらの記事ではお家でも集中して勉強ができるような工夫を紹介しています↓
目標の変更・修正は随時行おう
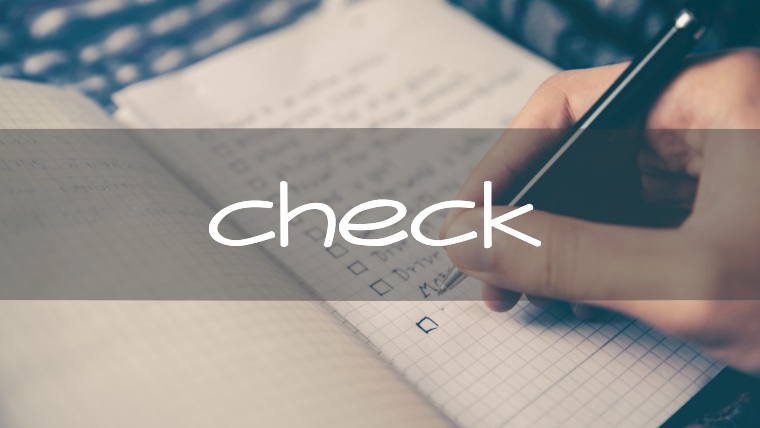
一度決めた目標は達成するまで変えてはいけない…というわけではありません!
将来の夢が変わることもあれば、日々の状況によってこれまで通り勉強できないこともあるでしょう。
新たな目標や生活スタイルに合わせて勉強内容を工夫していく必要があります。
特に工夫してほしいのは毎日の「小さな目標」。
毎日テキスト1ページが余裕だったらもう少し負荷をかけてみたり、逆にすごく負担になってしまうようならもう少し減らすなどの調整が必要です。
そして志望校など「大きな目標」が変わったときは、そこに向かう過程の「小さな目標」も変わってくるはずです。
目標や進捗を「見える化」しておけば勉強量の調整や目標の上方修正・下方修正もしやすいです。
ぜひ自分のやりやすい方法でして記録していってくださいね。
まとめ:目標を立てて勉強することこそが成長につながる
- 目標を立てることはモチベーション維持や現状との距離を把握するためにも大切
- 基本的には「大きな目標」を決めて「小さな目標」に落とし込んでいこう
- 目標や進捗状況の「見える化」が大切
- 目標は随時更新していこう
今回は勉強の目標の立て方を例を用いて解説していきました。
大きな目標までの道のりは遠く険しいような気がします。
しかし道のりを分割して「小さな目標」に落とし込んでいけば、具体的にとるべき行動が見えてきますよね。
目標がある人とない人とでは目の前の課題に対する挑み方も変わってきます。
小さな目標を達成していくたびに大きな夢に近づいていくと考えると、俄然やる気が出ますよね。
夢を実現するために今できることを少しずつやっていきましょう!